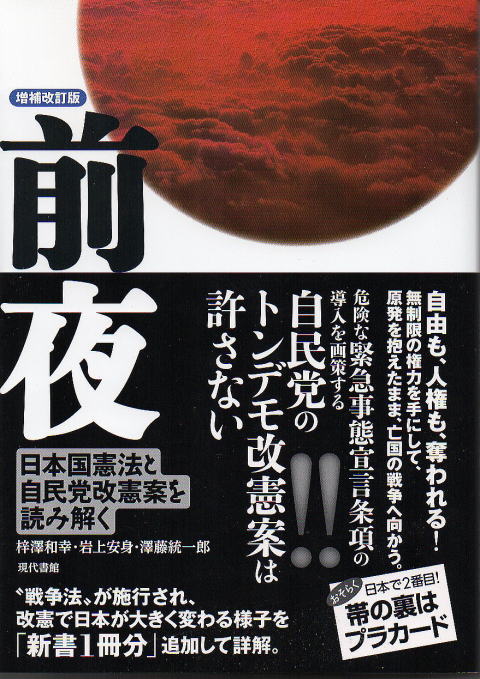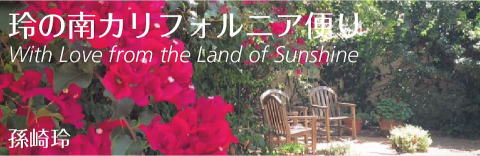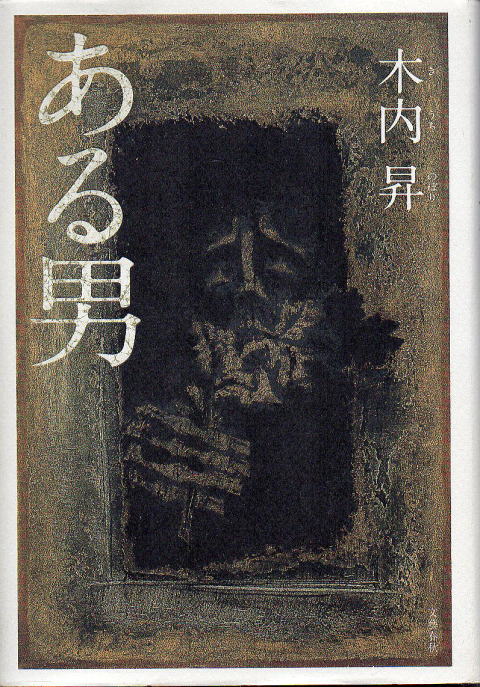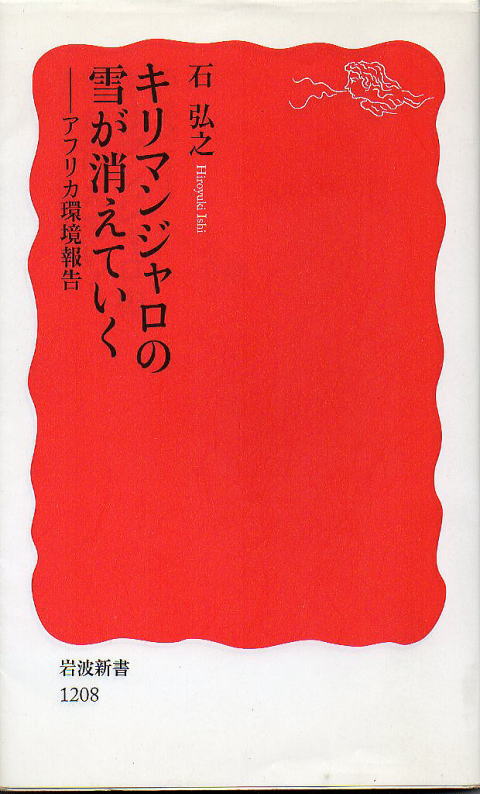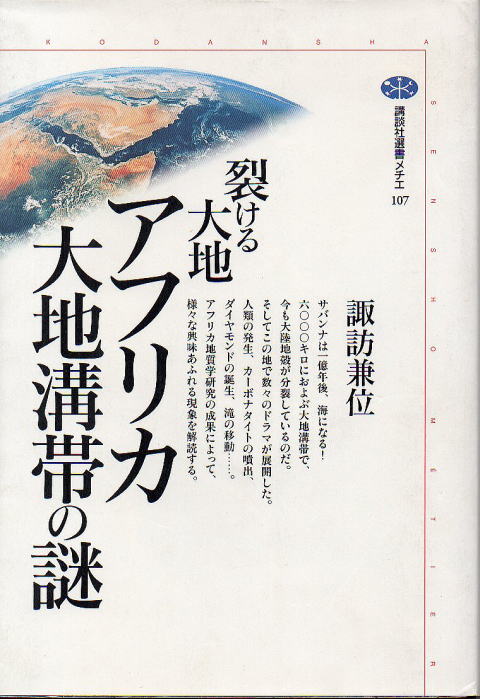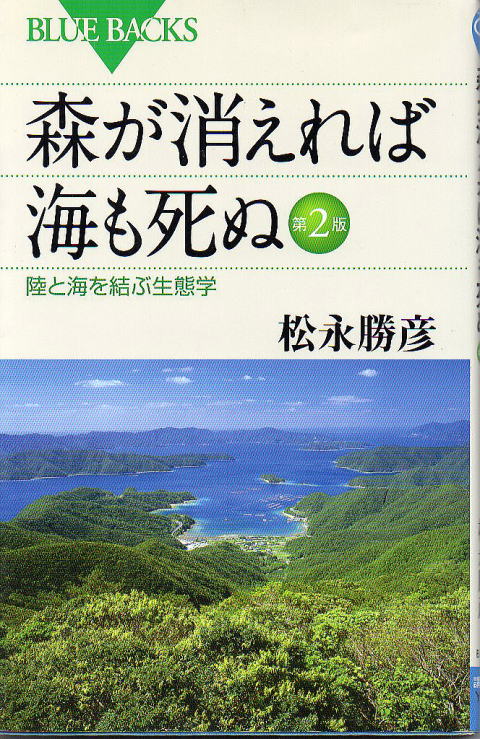怒れる土着日本人 ちょいと見 E-mail: hoku@pc.nifty.jp 時間/空間/環境/出来事つれづれ


(2016年2月28日)
☆ 書籍紹介 「増補改訂版 前夜」
梓澤和幸・岩上安身・澤藤統一郎 著:「増補改訂版 前夜」
(現代書館,2015年12月,2,500円+税)
2016年7月の参議院議員選挙で自民党・公明党およびその応援勢力の合計が,議席の2/3以上を占めた場合,まず緊急事態が発生した場合を想定して,その場合に総理大臣に国の全権限を集中させる「緊急事態法」を単独の法律として自民・公明などの多数で制定強行し,その制定した緊急事態法を根拠にして,あの忌まわしい70年以前の不幸な時代の「戒厳令」のように,アベ首相が緊急事態の宣言をして,現憲法を含む全ての法律を停止した上で,その緊急事態宣言状態の間に現憲法を破棄し,自民党の改憲草案を新憲法として制定強行しようと目論む,アベ政権の憲法改正(改悪)の危険が透けて見えている.
それはまるで独裁・ファッショそのもので,多くの日本人が忌みじく嫌っているあの北朝鮮の政治体制そのものだ.紹介の書籍「前夜」は,その自民党の改憲草案を現憲法との比較で具体的に読み解いた,389頁におよぶ緊急出版の力作.
自民党の改憲草案は経済の発達した民主主義の先進国では,とてもとても考えられない,それはオドロオドロしい内容で,一言で言えば人々・国民の自由と権利をいかに侵害・剥奪するかを定めようとする改憲案だ.もはや自民党は自由民主党ではなく「自由独裁党」と党名を変えた方が当たっているように思える.「緊急事態」条項なんて自由を剥奪する戒厳令そのもので民主主義を否定している.
分厚い書籍にも拘わらず,読みやすくまた現在の日常生活における身の保全・守り方など,現実的に役立つ法律の考え方・対処なども述べられていて非常に興味深い.
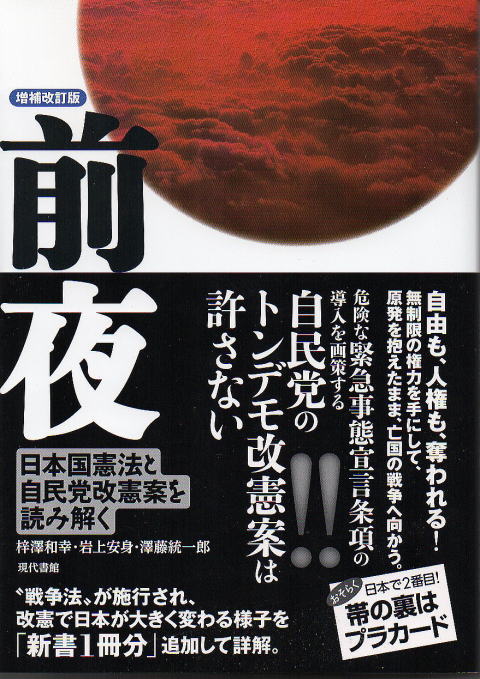
(2015年9月9日)
☆ 孫崎玲さんの随筆
アメリカ西海岸からの爽やかな風がここ日本までそよいでいるかのような感覚を覚える,出版社の「左右社」のブログに掲載されている「孫崎玲」さん(米国,チャップマン大学准教授)の随想にリンク.
http://sayusha.com/webcontents/c12/p=201608141900
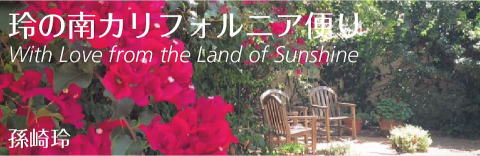
(2015年7月8日)
☆ ギリシャの経済危機と国民投票(2015年7月5日)の結果は「NO」
ギリシャの債務返済不履行による国家経済破綻デフォルトの話題が世界を駆け巡っている.ギリシャが破綻をした場合の世界経済への影響,日本経済への影響はどうなるの?.と日本経済新聞,ウォールストリートジャーナル,ロイター(日本語版)を始めとした色々な新聞を読んだが,.ギリシャ人は休憩が多すぎてあまり働かないとか,年金が多すぎるとかの記事報道ばかりで何か要領を得ない.特に日本の経済学者?のような人の記事なんて全く真相を見ていない中身の薄い腑抜けのようなものばかりだ.ましてテレビなんて面白半分揶揄半分のゴシップ的な報道ばかりだ.
そもそもギリシャの債務は,何時どこで誰がどこから借りて何に使ったのか,その時の責任者は誰だったのか,利子利率は現在どのようになってるのか,今までどのくらいの利子を払っているのか,債務元本はどうなっているのか,国民の生活は実際はどうなっているのかなど,基本情報が皆目不明のまま伝えられないまま,ただセンセーショナルにEUの要求を受け入れるのか受け入れないのか,「YES」だ「NO」だ「NO」の場合は「ユーロ離脱」だ云々などばかりが報道されていた.ほんの少しの期間だが随分以前にギリシャ人留学生の青年とトルコで一緒に仕事をしたよしみのギリシャ贔屓の者としては疑問が尽きない.
話を少し冷静に整理すると,ギリシャの「チプラス首相」は国民投票でEUの要求を受け入れない「NO」の選択結果がなされても「ユーロ離脱はしない」と言明している.そもそもユーロ加盟規定には,たとえ債務不履行になった場合でもその国が自ら離脱を申し出なければ離脱を強制することは出来ないことになっている.
どうやら構造的には,ドイツ・フランス中心のEU側が,ユーロに残りたい多くのギリシャ国民の希望をテコに,EU側の条件を受け入れろ「YES」と言え,受け入れないで「NO」ならば「ユーロ離脱になるぞ」と脅かしている構図が正確なようだ.今回ばかりはドイツのメルケル首相女史も何かいつもの賢明さが見えない.
何か話が少しおかしいな?,そもそも債務のそもそも論はどうなっているの?,そう思って記事を検索していたところ,下記の「ATTAC Japan」の記事とそのリンクを目にした.それは,第三世界債務帳消し運動のパキスタンの方からの要請文書(原文・英語)をATTAC Japanの方が日本語訳したものですが,かねてから感じていてまた知りたかったギリシャ債務問題の発端と原因などそもそも論の本質的な疑問点が率直に記述されています.これらの疑問点は日本内外のニュースではなかなかお目にかかれない視点なので,以下にリンク先を紹介するほか,少し長いですが「ATTAC Japan」による日本語訳文を転載します.
ATTAC Japan リンク: http://attaction.seesaa.net/article/418877621.html
第三世界債務帳消し運動(CADTM)パキスタンのサイード・アブドル・ハリク(Syed Abdul Khaliq)さんからの要請です。原文(英語)、世界各国の賛同者のリスト、署名フォーマットは
http://cadtm.org/Appeal-to-support-the-Resisting
拡散に協力をお願いします。
喜多幡
----------------------------------------------------------------------------
署名を!
ギリシャの抵抗する人々と公的債務真実委員会を支持するアピール
CADTM(第三世界債務帳消し国際運動)のアブドル・ハリクさんより
全ヨーロッパと全世界の人々へ
緊縮政策に反対し、不当な公的債務 – 私たちの知らない所で、私たちの利益に反して合意され、私たちを窒息させようとしている – の返済を拒否するすべてのみなさん。
このアピールに署名する私たちは、2015年1月25日の選挙での投票を通じて、北半球で初めて緊縮政策の政治 – 人々の知らない所で、人々の利益に反して、トップの地位にある人たちによって取り決められたいわゆる「公的債務」を返済させるために押し付けられた
– を拒否した最初の国民となったギリシャの人々を支持します。同時に私たちは、ギリシャ国会議長の提案によってギリシャ公的債務真実委員会が設立されたことを、ギリシャの人々だけでなくヨーロッパおよび全世界の人々にとって非常に重要な歴史的出来事であると考えます。
実際、ギリシャ国会の真実委員会 – 全世界のボランティアの市民によって構成されている - は他の国でもモデルとされるでしょう。なぜなら、第一に債務問題はヨーロッパと全世界の大半を苦しめている災禍であり、第二に何百万人もの人々が的確にこの債務について基本的、根本的な疑問を提起しているからです。
「この融資は何に使われたのか? 融資にはどんな条件が付いていたのか? 利子がどれだけ払われたのか、どんな利率か? 元金はどれだけ返済されたのか?
元金はどんな方法で返済されたのか? 人々の何の利益ものたらさない債務がどうやって累積したのか? 元金はどこへ行ったのか? どれだけが不正利用されたか、それは誰によってか、どういう方法でか?
さらに、誰が、誰の名義で融資を受け取ったのか? 誰が、どういう立場で融資を認めたのか? それに国家はどのように関わったのか? どのような決定によってか、また、どのような承認手続きによってか?
私的な債務がどうやって公的債務になったのか? 誰がそんな不適切な仕組みを作ったのか、誰がそれを後押ししたのか、誰がそこから利益を得たのか? その資金でどんな違法行為や犯罪が行われたか?
なぜ、その民事、刑事、行政責任が問われてこなかったのか?」
これらの疑問はすべて、委員会 - 「公的債務の出現と不釣り合いな増大に関連するすべての情報を収集する」権限を公式に与えられている – によって徹底的に分析され、科学的な精査が行われ、それによって債務に関する覚書の対象期間
(2010年5月から2015年1月)、および先行する期間における債務のどれだけの部分が不正または違法、不当、もしくは持続不能であるかが判断されます。委員会は正確な情報を公表しなければならず、それはすべての市民に公開され、債務帳消しの正式の宣言を支持する根拠を示し、ギリシャの人々、国際社会、国際世論の中での理解を増進し、最終的に論点と要求を書き上げなければなりません。
私たちは、これらの疑問に対する明確で正確な回答を要求することがすべての市民の最も基本的な権利であると考えます。私たちはまた、この疑問への回答を拒否することは、「債務システム」
- 金持ちを一層金持ちに、貧しい人々を一層貧しくするためのシステム – を考案し、利用している最高責任者における民主主義と透明性の否定を示すものと考えます。さらに悪いことには、この最高責任者たちは、社会の運命を自分たちの手に独占しつづけることに汲々として、圧倒的多数の市民の決定権だけでなく、自分たちの運命と人類の運命を自分たちの手に取り戻す権利を奪っている。
だから私たちは、このかつてなく非民主主義的で、非人道的な新自由主義のヨーロッパを拒否するすべての市民、社会運動、エコロジーやフェミニストのネットワークと運動、労働組合、政治団体に、以下の緊急のアピールを発しています:
ギリシャの公的債務真実委員会とその活動 – ギリシャの公的債務の内、違法、不当、不正、持続不可能な債務を明確人する – を支持することによってギリシャの人々の抵抗運動に連帯を示そう。
公的債務真実委員会とその活動を、ギリシャ国内および全世界の、「債務システム」に関する真実を隠蔽しようとしているすべての勢力からの激しい攻撃から守ろう。
ヨーロッパや世界各地で取り組まれている市民の債務監査に積極的に参加しよう。
あなた方の支持、連帯をあなた方の社会的ネットワークで共有しよう。なぜなら、この支持と国際連帯こそが、私たちの共通の敵、緊縮政策と私たちを絞め殺そうとしている債務に対して闘っているギリシャの人々に対する支配権力の攻撃を止める唯一の手段だからです。
私たちの敵は、経験豊富で、団結していて、見事に連携していて、強力な権力を持っており、私たち – 私たちの社会の圧倒的多数を占める人々 - に対する攻撃を最後までやり遂げることを固く決意しています。私たちはバラバラになって、それぞれが自分の領域だけで闘っているという余裕はありません。だから、ギリシャの抵抗闘争との連帯、ギリシャ国会の真実委員会への支持、そしてそのような債務監査委員会を可能なあらゆる所へ広げるための巨大な運動へと私たちの力を統一しようではありませんか。なぜならギリシャ人民の闘争とその勝利は私たちの闘争であり、私たちの勝利であるからです。団結こそが私たちの唯一の力です。団結すれば私たちは抵抗でき、分裂すれば倒れる。
サイード・アブドル・ハリク
(Syed Abdul Khaliq)
Executive Director,
Institute for Social & Economic Justice (ISEJ)
Focal Person, (CADTM) Pakistan
----------------------------------------------------------------------------
上述のギリシャ議会「債務の真実委員会」に関しては,しんぶん赤旗に興味深い読み応えのある記事が掲載されていた.債務の真実委員会によればギリシャの債務は,あのアメリカのサブプライムローンを発端とする世界金融危機時に,不動産バブルで沸いていたスペインやギリシャへ大規模投資を行っていて危機的状況に陥ったドイツやフランスの金融機関救済措置としてギリシャの債務危機が生じたと言うのが真実のようだ.
なるほど・・日本の「サラ金地獄」の取り立てや,バブル崩壊時の政府の「金融機関救済」と同じ仕組みかァ・・.ここは今は亡き「ナニワ金融道」の作者青木雄二氏にご登場願いたいところだ.どうやら「おんどれの目ん玉売らんかい!」「臓器を売らんかい!」を,「年金減らせ!」「増税しろ!」に言い換えるとわかり易いようだ.しかし貸し手責任と言うものがあるだろう.ユーロ債権団が高利貸しのサラ金のようになっている構図だ.そう考えると色々な辻褄が合う.
どうやら同じように現在経済危機に陥っているスペインも同じ根底に基づいているようだ.ヨーロッパ好きな者,特にフランスやドイツ好きなものとしては,両国が中心を担っているそのあこぎなユーロの債権団の仕掛けを書いた見逃せない記事だ.日本国内ではほとんど報道されていないその「債務の真実委員会」の奥の深い興味深い記事は読み捨てにするのも「もったいない」ので以下に転載する.
支援口実の金融機関救済
欧州の専門家意見 (パリ=島崎桂,2015年7月7日,しんぶん赤旗)
2010年以来続くギリシャ債務危機-。専門家や研究者からからは、経済危機に陥った金融機関の救済策が、債務危機を招いたとの意見が上がっています。
ブリュッセルの欧州議会で2日に開かれた会合「周辺国の債務-原因、結果、解決策」(既報)では、招待を受けた日本共産党の代表も参加し、ギリシャなど南欧諸国が債務危機に陥った背景や対応策を議論。報告者の1人で、ギリシャ議会の「債務の真実委員会」に加わる政治学者エリック・トゥサン氏は、「商業銀行の経営危機がギリシャの債務危機にすり替えられた」と主張しました。
ギリシャの債務危機が注目されるようになる前の07年、サブプライムローン問題を発端とする世界金融危機が発生。それまで不動産バブルに沸いていたスペインやギリシャへの大規模投資を行っていたドイツやフランスの金融機関は経営危機に陥りました。しかし、トゥサン氏によると、ギリシャやスペインはこの時点で「債務危機に陥る状況にはなかった」といいます。
その後、欧州主要国政府は、金融機関の救済を試みますが、金融危機と経済不況を招いた張本人である銀行などの救済に向けた財政支出は、世論の賛同が得られません。そのため「多額の政府債務と過度な財政支出が危機の原因だとする状況を作り出し」(トゥサン氏)、ギリシャ支援を口実とした金融機関救済が行われました。
実際、欧州連合(EU)や欧州中央銀行(ECB)、国際通貨基金(IMF)によるギリシャへの「救済」融資の大半は、各国金融機関への利払いや債務返済に充てられました。国内では、融資条件として課された過酷な緊縮政策で失業や貧困が急速に広がり、国民生活は悪化の一途をたどりました。
トゥサン氏は、こうした状況でも財政が枯渇するまで債務返済をギリシャ政府の姿勢を評価。国民投票実施への賛同を示し、「国家主権に基づいた力強い姿勢がなければ、債権団からの譲歩引き出すことはできない」と訴えました。
トゥサン氏と共に報告を行ったリスボン大学経済・経営学スクールのペドロ・レオン氏は、南欧諸国の債務返済の利息が、平均でGDP(国内総生産)の4%に達していると指摘。利払いが財政を圧迫し、自由な経済政策を妨げることで「購買力や生産力を低下させ、さらに失業率を高めている」と訴えました。
こうした状況から脱するため、レオン氏は「公的債務の利率0%」の導入を提案。具体策として、ECBによる公的債務の直接購入を可能とする法改正を求めました。
(2015年7月8日) *赤文字は管理者
追記:
その後ギリシャのチプラス首相は,EU債権団との交渉で頑張っていたギリシャのバルファキス財務相を解任(本人が辞任)し,国民投票後の交渉で国民の多くが拒否をした筈の「年金削減」や「年金支給年齢を2年延長して67歳からの支給延長」や「増税」案などをEU債権団に提示し,国民投票の結果とは正反対のことをやっているとの反発を招いている.
もしかしてなのだが,しっかりと国民の声を聞いて政策を遂行しようとしていたのは実は「バルファキス元財務相」で,チプラス首相はただ単なる調子の良い男だけなの?.疑問が生じている.そういえばバルファキス元財務相は物言いが奔放で,EU債権団の虎の威を借りただけの髪型ツンツンのEUの若い交渉者は"この青二才が!"とばかりにバルファキスに相手にもされず,債務側権限の金の力で簡単にはねじ伏せることが出来ないことから,随分とはらわたが煮えくり返っている様子が映像からも見て取れた.今後を注視したい.(2015年7月12日)
★ 自然科学書の「大久保書店」の店主「大久保 雄一」氏逝去
地質関連書籍の古書を専門に取り扱う日本で随一の書店,本の街神田神保町1丁目にある「大久保書店」の店主「大久保雄一」氏が,本年2014年7月28日に75歳で逝去されたことを葉書で知った.
大久保書店は知る人ぞ知る,地質関連の自然科学書を取り扱う「聖地メッカ」の様な存在の古書店で,地質を志した研究者・学生・技術者ならば,東京に出たら一度は訪ねる価値のある古書店で、ここで貴重な文献・資料も入手出来る.
書店の始まりは,あのノーベル物理学賞受賞者の「湯川秀樹」氏の父,地理学が専門で当時の東大教授「小川琢治」氏と,大久保書店の先代との間の懇意な交流がその発端あったことは,下記の神田神保町書店「JIMBOU」のオフィシャルブログサイトに紹介されている.
その中に,日本の自然科学研究者の研究資料や文献資料の散逸を守る,文化的拠点としても意義のある書店への熱心なすすめがあったことは,当方も来店の折りに店主の大久保雄一氏から,先代から書店を引き継いだ時の経緯などを含め話をお聞きした事がある.
大久保書店紹介:http://jimbou.info/town/ab/ab0026.html
長年の貢献に敬意を表する.後継は「大久保 直樹」氏(2014年11月29日).
☆ 書籍紹介 「ある男」
木内 昇: 「ある男」 (文芸春秋,2012年9月,1600円)
専門書ではないが久しぶりに興味を持って読めた本.慶應大学の金子勝氏のツイッターの中で,書籍紹介がなされていたので書店に寄って購入した.
2009年12月号~2012年5月号までの文芸春秋社「オール読み物」に掲載された7編の短編からなる書籍.描いた時代は今からおよそ145年前頃(1868年)からのその後が舞台.江戸幕府の幕末時代から大日本帝国の明治時代に体制が変わる激動の時代に生きた,地方の名も無い人々が受けた時代の風,矛盾,生活感覚や時代認識など心の中を辿って描いたもの.なお,木内氏は直木賞作家で女性.
書籍帯封の紹介は 「日本近代の産声にかき消された叫びと祈り ・・・中央政府の大義に屈せず、彼らはそのときたしかに生きた」.「地方は、中央に隷属しているわけじゃあないのだぜ」となっている.
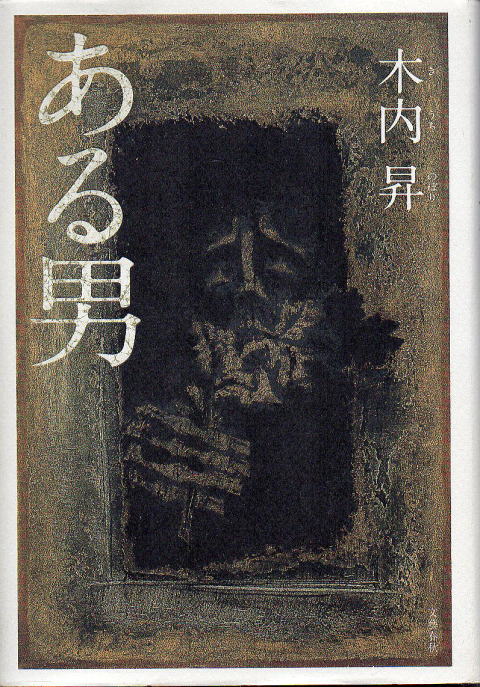
7編の作品は一見すると幕末から明治初期にかけての坂本龍馬的な,中央政府と地方の志士・人々の,時代の揺らん期における軋轢・心の葛藤のように思っていたが,読んで行くうちに著者の本当の意図は,現在の日本国民が直面している混乱した国内政治状況が,実は100年以上も昔とうり二つで数々の共通性を有していることに着目し,その共通した思考を作品の横軸として,縦軸にその当時に起きた出来事を取り上げ,その中へ地方の名も無き男達の思考過程として編み込むことで,現代日本社会の政治状況の非民主性,人間の非進歩性(今も昔も同じ)をあぶり出しているかのようだ.
例えば第4編の「女の面」では飛騨の地役人,現代の地方公務員に相当するような八方美人の男・・言い換えれば,しきたりを守り上位下達と周囲に波風を立てない事で自身の保身をはかる男を登場させている.時の新制県知事による年貢増税に苦しむ民百姓の請願訴えがあった時,その訴えを受けた地役人の男の対応は,これまで男の長年の保身経験から”話を聞いてさえやれば民百姓の気が治まると”踏んだ,親切顔のガス抜き対応で民百姓の訴えを逸らそうとしたが治まらず,請願の民百姓の問い詰めに窮地に陥った男に吐かせた言葉が
----------------------------------------
「うるさいっ! 生意気言うな お前らなんぞ黙ってわしらの言うことを聞いて、汗の涸れるまで働いておればいいのじゃ。このっ、能なしのっ、水呑百姓めがっ!」
----------------------------------------
の本音であった.この地役人の表面的なガス抜き対応とその本音・精神は,現在の日本の大手メディアと政府とのスクラム政治,真実を隠そうとする思考・精神と共通性を有していて,日本社会・日本政治の非進歩性を端的に指摘しているものと読めた.
また,第7編の「フレーヘードル」では(オランダ語で自由),明治11年を舞台にして岡山県地方の中農の家に育った傍目には寡黙で控えめな26歳の青年を登場させ,この地方の青年がふとっ手にした新聞の「国会開設懇請議案」の記事を目にし,これまで男の頭の中で形不明で渦を巻いていた国と地方のあり方に目覚め,中央政府の国会開設の政治活動に関わって行く過程の思考を描いている.その過程で男は才能を認められ国会開設の建白書の草案を練るに至った.
この建白書の強調点は,
”全国一般中位下等という点を、とりわけ強調して進めていく。知識層が中心の民権家のみならず、農民も商人みな参政権を欲し、政治に関心を持っているとし、その請願が差し迫ったものであることを訴えた”「民意の強調」の点にあった.
その後,紆余曲折を経て明治14年に天皇が国会開設の詔(みことのり)を降下して国会開設が決定に至ったが,この短編の最大の見所は,国会開設が決まった後の男の「私議憲法案」の草案を練る中での,男の姑からの問いに対して男に吐かせた言葉にある.それは、
----------------------------------------
「わしの草案が柱とするのは、民意を抑える、ということにございますのじゃ」
「ほう民意を?」
「ええ、抑えるのです。なにも見えよらんのに、大きな声で主張を唱えれば世を変えられると信じようる者を潰すことです。国会は選び抜かれた者のみが発言できる場にせねばならん。国を作るのは確かな目を持つ者だけが許されることなのじゃ。そのためには、痴れ者がたやすく足を踏み入れられんよう、はじめにしっかり枠組みを作らねば収拾がつかなくなりますけぇ」
「民衆を使って事を起こすにはここまでじゃ。これからはもっと高みを目指さねば、また繰り返しになる」
----------------------------------------
著者は人間の心がその地位とともに変節して行くさま,怖さを赤裸々に描いていて,現代社会の政治家・役人の心や行動・精神意識が,実は100年以上も前のそれと全く変わっていないことに着眼している.いずれの短編も人間の心の変節や狡猾さを軸に据えた,読み応えのある骨太の作品で久しぶりに堪能出来た秀逸作品.(2013年5月4日).

☆ 書籍紹介 「キリマンジャロの雪が消えていく-アフリカ環境報告書」
石 弘之 著:「キリマンジャロの雪が消えていく-アフリカ環境報告書」
(岩波書店_新書版,2009年9月,780円)
新聞社編集委員,ニューヨーク特派員から東京大学大学院教授,ザンビア特命全権大使,北海道大学大学院教授を経て現在東京農業大学教授の著者が,国連環境計画(UNEP)上級顧問,東中欧環境センター理事,国際協力事業団参与などを歴任した経験をもとに,アフリカへの思いを凝縮した著者最終章となる渾身の書.
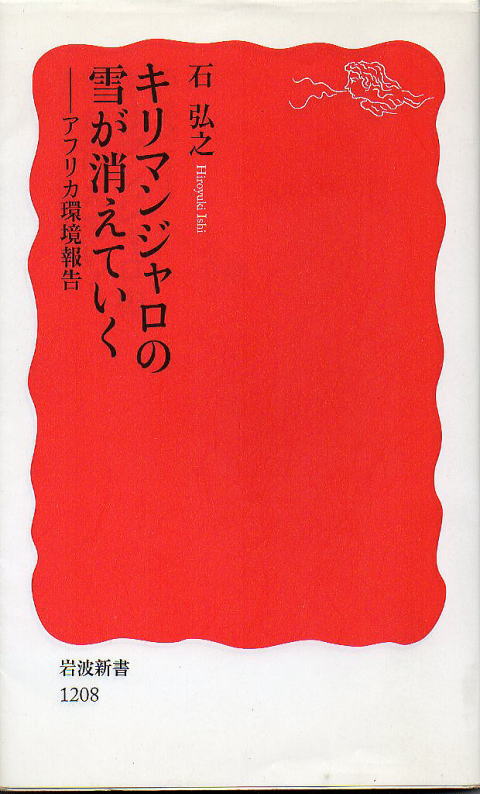
過去2回,タンザニアのキリマンジャロ上空を飛ぶ旅客機の中から,その山頂を目にした事のある者として,キリマンジャロと言う標題にひかれて,懐かしさ半分に書店でふと手に取って読んだ本ですが,その内容はキリマンジャロの雪の消失に表れている気象変動問題のみに留まらず,中心は書籍タイトルの副題に示されるように,アフリカ大陸全体に関わる森林や動物など動植物全体の生物種の急激な消失,爆発的な人口の増加と人々の生活環境の諸問題を,これまでの著者の豊富な体験をもとに分析指摘し,さらにその解決策をも模索する情熱溢れる書.またその指摘はアフリカの環境問題を超え,地球の限界・人類未来への危惧へとも連なっている.
この書で特筆される視点は,気象がどのように変化しているとか,動植物がどのくらい減少しているかなどの,ただ単なる環境を報告した書ではなく,アフリカの環境問題は,実は欧米を始めとした先進諸国による天然資源の収奪に端を発していて,それが
「一部特権階級の政治腐敗を招き,貧富の差を拡大し,利権の奪い合いからしばしば紛争を誘発する.天然資源がいまや「呪われた資源」になってしまった.」
(同書P108)とする,環境問題の根底を見据えた的確で鋭い洞察力・認識力にある.
先進諸国による天然資源の収奪がその国の政治腐敗を招き,利権の奪い合いから紛争が生じ,その結果,多くの人々の命が失われ,また多くの貧困層が生まれる.その為,人々は生きるために樹木を伐採したり動物を密漁して生活の糧を求めざるを得なくなっている.その結果,森林の破壊が一層促進され大地の砂漠化が進み洪水や干ばつの自然災害につながって,人間を含めた生物生息環境の悪化や種の絶滅に拍車がかかる悪循環に陥っている.
コンゴ民主共和国(旧ザイール)南部で筆者が遭遇した盗伐現場での生々しい経験も記述されている.
「アフリカでは違法伐採はどこでも普通に見られる。コンゴ(民)南部の森林地帯で、道端に伐採したばかりらしい大木が積み上げられていた。車から降りて写真を撮ろうとしたら、物陰から現れた数人の男にパンガ(山刀)やチェーンソーで威嚇され、あわてて逃げだしたことがあった。盗伐した木材を運び出していたところだった。木材は採掘や精錬の手間がかからず、入手が容易な資金源である。武器弾薬など巨額の資金が必要な内戦や内紛が、貧困国の多いアフリカで長期化する最大の理由は、地下資源とともに、違法木材の取引が紛争の資金を支えることにある。」(同書P112).
このような違法伐採に先進諸国の企業が密接に関わって現地の闇ルートを支え,アフリカの森林の著しい減少,生物生息空間減少の環境破壊に手をかしている.それとともにゾウ,カバ,バッファローなどの大型草食獣から,ゴリラやチンパンジーなどの霊長類,さらには小鳥やトカゲ,カタツムリなどの小動物いたるまで,多くの種類の野生動物がブッシュミートして捕らえられ,現地の人々の食料や欧米のレストランへの輸出用として多くの動物が殺され,特に近年は狩猟容易なチンパンジーとゴリラの霊長類が狙われていることも指摘している.
読んでいてどうにも出来ない絶望と,地球と人類・生物の暗い未来を感じてしまうような書籍ではあるが,著者はあとがきで
「貧困や環境破壊の大波に翻弄されるアフリカを救い出す特効薬は、これまでのところ見つかっていない。多分、そうしたものはないだろう。これからも、さまざまな試行錯誤を繰り返しながら、人智を尽くした総力戦を展開するしかない。」
とその未来への努力を述べている.アフリカに情熱を尽くした著者の心からの言葉と感じる.
また,本書では日本の海外協力援助(ODA)の実態経験や,日本のODA援助に対する受け入れ国側でしばしば語られている認識,「ODAは日本人と日本企業のためのもので、この国の役にたつものは多くない。」が述べられている(同書P208~209).これら認識を私達は真摯に受け止める必要がある.
本書で述べられている内容は,遠いアフリカ大陸だけに限る問題ではなく,未来に接続可能な地球環境を考えて行く上で,現在の日本にもあてはまる問題を示している.高い・速い・大きいだけの大量消費型社会ではなく,必要なものを必要な分だけ使う,低エネルギー型社会への転換が今強く求められている.(2011年10月9日)
<<追記>>
本を読んだ中で少し驚いたことがあった.それは著者がこの本のあとがきの中で,名古屋大学名誉教授の諏訪兼位氏に感謝の意を表していることだった.
諏訪氏はいわゆる環境分野ではなく,どちらかと言えば,私達のような業務分野の人間に身近な,地質学の研究者ですが,アフリカ大陸の地質に非常に詳しく,1962年に第一回名古屋大学アフリカ調査団の一員(団員5名)としてアフリカ大陸に渡っていて,ジプチ,エチオピア,スーダン,エジプトで50日間におよぶ地質巡検をし,当時においてアフリカの大地溝帯の調査も行っています.
現在でしたらアフリカ大陸諸国も,観光などで容易に訪れる事の出来る国々ですが,1962年と言えば戦後まだ17年,日本は1ドル360円の固定相場制の時代であり,海外へ出るにしても国からの外貨準備割り当てを得る必要があった時代なので,そのような時に遠いアフリカ大陸の地質調査を行ったのは並大抵のことではなかったものと推察します.
そのアフリカ大陸調査の成果の一部は,一般教養本として「裂ける大地--アフリカ大地溝帯の謎」として講談社選書メチエ107として1997年に出版されています.この書籍は非常にわかりやすく,また詳しくアフリカの地質および自然史が述べられているとても素晴らしい本です.
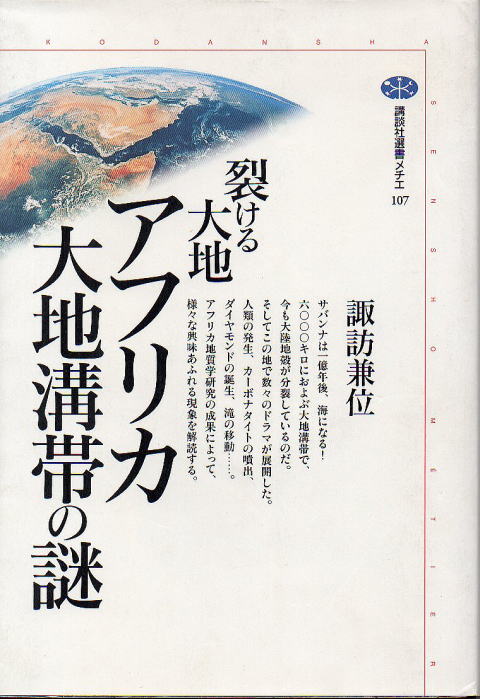
その地質学者の諏訪氏が,著者の石氏と接点があったことは嬉しい驚きでした.良く考えれば著者のアフリカ環境学は,地質分野の自然科学をも包括する分野ですので当たり前と言えば当たり前でしょうか.人間は自然とともに生きて来て,自然とともに未来へ向かうのですから・・・.著者石氏の情熱を込めた渾身の書にもう一度敬意を表します.
☆ 書籍紹介 「石油の生産量はピークに来たのか」
根岸 敏雄 著:「石油の生産量はピークに来たのか」(石油文化社,2006年4月,1,500円)
■ 書籍概要
少し古くなってしまいましたが数年前に出版された石油資源に関する書籍.石油資源を開発するには大規模で高精度かつ最先端の物理探査や化学分析技術が常に用いられ,より一層精度を高めながら開発探査が行われています.私達の土木建設分野の地質調査や土壌浄化の技術においても,それら石油探査技術の一部を小規模に応用発展させている技術も多く,その規模は全く違いますが石油資源開発の探査手法とその技術には学ぶものがとても多くあります.
著者は,地質技術者として長年に渡って主として中東の資源開発や石油操業会社に携わって来ましたが,その豊富な経験をもとに石油埋蔵量の現状認識や考え方,21世紀のエネルギーの可能性,掘削技術などについて,国際的な技術動向なども踏まえて石油資源(エネルギー資源)の現状と未来について,地質技術者の目線でわかりやすく解説しています.また<参考>として所々のコラム欄に書かれた現地での風景のひとこまなどは,私達が直接には知ることの出来ない興味を引く内容が記されています.
ピークオイル論とは同書によれば「埋蔵量をどの位残した時点で(あるいは埋蔵量をどれほど消費した時点で)生産の増加が頭打ちになり減退に向かうのかが問題であり,その時点の議論がいわゆるピークオイル論である。」と述べられています.平たく言えばそのピークは埋蔵量のほぼ半分の量を消費した時と言うことになります.
■ 可採埋蔵量
推定する究極可採埋蔵量などによる不確実性はあるものの,上述のピークオイル年は2000年~2032年前後と予測されていて,現在の2010年は石油の枯渇の過渡期もしくは下降段階に入っていると考えられています.車の登場で石油(ガソリン)の使用が増加し始めたのがおよそ今から100年程前で,急激に増加したのが第二次世界大戦後の60年程前からですので,可採埋蔵量と消費量などとの関係にもよりますが,単純に考えれば石油枯渇するまでの残りの年数はおよそ上述の期間と同じ程度と見ておけば良いかも知れません.
財団法人 日本エネルギー経済研究所 石油情報センターのホームページ(http://oil-info.ieej.or.jp/whats_sekiyu/1-5.html)によれば,今の所,可能採取年数はおよそ「50年程度」と見積もられています.これまで全国に林立していたガソリン給油所が徐々に整理・統合され廃業が増加しているのも,このピークオイル論を基にした石油の枯渇減少予測と,それによる代替エネルギー開発,省エネ技術の開発などによる石油需要の減少予測に連動しているものと考えられます.
■ 深海での石油開発と事故
2010年4月20日に,アメリカ合衆国ルイジアナ州のメキシコ湾沖合80kmでの,英国BP社による半潜水式の大水深海底石油掘削リグの爆発炎上による,掘削井からの大規模な原油流出事故が発生しました.この事故は発生から2ヶ月以上も過ぎた7月現在も大量の原油流出が止められず,地球規模の深刻な環境汚染にまで発展していて,深海での石油資源開発の困難さ掘削の是非などの問題点が浮き彫りとなっています.同書の中では深海(大水深)での掘削技術や,2006年時点までのメキシコ湾での大水深の海底下での主要な油田の開発状況が示されています.
★ この史上最悪の石油大手BP社のマコンド海底油井からの原油流出事故は,2010年9月18日に完全封鎖の見通しである事が同社から示された.
■ 石炭の復権はあるのか
同書の第Ⅲ章には「代替エネルギーとしての石炭の復権はありうるのか」の章が設けられています.石油以前の世界のエネルギー源は,数世紀の長い間に渡って石炭が用いられて来ました.日本国内の自前エネルギーとしての石炭の生産は1990年代の主要炭鉱の閉山と,2002年12月に釧路の太平洋炭鉱の閉山で国内における石炭の供給は全て終了しました.しかし,全世界の埋蔵量としての石炭資源はまだ膨大な量が残されていることから,石油の枯渇減少とともに,CO2排出抑制などの環境問題を解決し,クリーンな石炭として次世代エネルギーに転換するまでの過渡期の補助的エネルギー源として,石炭の復権と利用拡大の可能性が見込まれています.またすでに褐炭の液化,石炭の液化やガス化利用などの技術は研究開発され実用化もされています.
第Ⅲ章の最初のページに,2005年12月に著者が撮影した,閉山した北海道の炭坑の写真(旧住友赤平炭鉱の立坑跡)が載っています.若き日の地質技術者としての著者の思いに至るとともに,一度だけですが住友赤平炭鉱がまだ操業していた頃の昔に,この立坑を訪れたことのある私としても,時代を経て静かに復権の時を待っているかのような,その立坑の姿にふっと郷愁の感を覚えてしまいました.
(2010年7月1日).
<<追記>>
その後,著者はもう一冊の下記著作を出版しエネルギー問題を考えている(2013年5月4日).
「化石エネルギーの今とこれから」 (諷詠社,2011年11月,1,200円)
☆ ふたつの「日本総合研究所」
■ 全く同じ呼び名のシンクタンク
全く同じ呼び名の「日本総合研究所」と言うシンクタンクがあるのをご存じですか,ひとつは「財団法人」で,もうひとつは「株式会社」の日本総合研究所なのですが,しかもお互いに同じような領域分野の分析・研究などの事業活動をしているのですから,第三者としては紛らわしくまた間違いやすい事この上ありません.
「財団法人 日本総合研究所」はテレビなどにも良く出演し,広い視野と世界観から問題の根幹を的確に捉え,鋭い見解を発信している寺島実郎氏が理事長を務める公益的なシンクタンクで,1970(昭和45)年8月に元東京大学総長の茅誠司氏等によって当時の経済企画庁や通産省の認可を受けた機関としてスタートしています.
一方,株式会社日本総合研究所は,1969(昭和44)年2月に住友銀行から分離独立した「日本情報サービス株式会社」からスタートし,1989(平成元)年12月に「株式会社 日本総合研究所」に社名変更をした三井住友フィナンシャルグループの民間シンクタンクとなっています.
情報を商いとする会社が自らの社名を変更をしようとした時,すでに存在している組織と全く同じ名称を用いることは普通ならば無いと考えますが,同社は同じ名称を選択しています.情報収集力の小さい零細企業だったならばともかく,社会的にも大きな組織グループに属し,また情報を商いとする会社ですので,商標などをはじめとしたネーミング使用などには,より一層に先進的で敏感なアンテナを有しているものと認識していますが不思議ですね.私達には見えない底辺の所に,実は太いつながりが有ったなんての特殊事情でも存在していたのでしょうか.
■ 情報内容の品質
過去のテレビ番組や記事などから見聞きする論考・論及など両者の情報の質を比較すると,少なくとも財団法人日本総合研究所の寺島実郎氏の内容の方が,世界認識や時代感覚,またその内容の深さなど多くの点において優れていることが感じ取れ,興味と関心を持って見聞きしています.
NHKや民放のテレビ番組の中で「日本総合研究所」の肩書きの方々が,専門家の立場から時々番組に登場し,時事の話題に対して分析・論及などを加える出演機会が増えているように感じていました.寺島氏とは別の人だけれども,日本総合研究所の他のメンバーの方々は,どのような見識・見解を有しているのかなと注目して聞いていると,案外に期待外れの鋭さに欠けた分析・論及の事をまま感じる事がありました.
おかしいなそんな程度なの?と気になって良く調べて見たら,実はそれらの人が株式会社日本総合研究所の方々だったことがわかりました.しかし困ったことに,登場する番組の中では,「日本総合研究所」の誰々と表示するのみで,「財団法人」なのか「株式会社」の人なのかは,不思議なことに画面にはいつも明示されていませんでした.高い見識を有する寺島実郎氏が属する「財団法人
日本総合研究所」の人の分析・論究・論及だからと,ある程度公平中立の目線からの質の高い情報提供を期待し,興味を持って聞いていたのですが,そうなると何か騙されて偽物を掴まされ損をした消費者気分になってしまいます.
どうも情報受け手側の視聴者個人として推察すると,番組提供者はそのようなことは最初から百も承知で,意識的な無意識で,財団法人か株式会社かの所属先明示を外しているような印象を受けてなりません.例えば経済などの銀行がからむ問題を論及するときに,三井住友フィナンシャルグループに属する株式会社の所属先が明示されて登場するのと,明示されないで登場するのとでは,情報受け手側の受け止め方に違いが生じます.そのあたりが少し意図的かなと思える情報提供の仕方と見える次第です.
■ 似たようなケースNHK
似たようなケースとしてNHK番組に登場する大学教授などによる専門家の解説などがあります.良く見るとその専門家は元々NHKの解説委員などをやっていた方々が大学教授などに転身し,その元身内の教授を呼んでその時々の議論のわかれる問題を,もっともらしく第三者的に解説させて放送しているケースが近年目立っています.意図を汲んであうんの呼吸が出来る元身内の第三者を招いての解説・論及は,公正中立性に欠ける疑義が生じかねず本来は避けるべき問題でしょう.それではまるで「やらせ」に近いものなってしまいます.
さて上述の日本総合研究所の件ですが,勿論,問合せがあればそのようなことは無いと否定はするのでしょうが,不完全な表示などを見ると誘導的な意図を感じてしまいます.いずれにしても情報の出所,質を判断する一つの要素としても,似たような組織があるのならば,その人の組織所属先を正確に明示することは,情報を発信する専門家知識人の方でしたら初歩中の初歩,常識・基本的な問題なのではなかろうかなどと考えてしまいます.
(2010年6月27日)
<<後日追記 2012年>>
① 上述の寺島実郎氏ですが,福島原発事故後の「原発に関係する発言」については,これまで氏の最大の特徴であった論理的発言が影を潜め,原発存続容認に聞こえるような発言が繰り返えされていて,これまでの寺島氏の論理的発言に敬意を表してきた人達の間からも批判の声の湧き上がりが見られる.
寺島氏は,原発の問題はただ単に日本だけの問題ではなく,アメリカとの複雑な政治関係の上から成り立っているので,まずアメリカと充分に話しあってから原発をどうするかを決めるべきだとの意見のようです.
しかしその考え方は,元外務省の孫崎氏の著書「戦後史の正体 1945~2012」,創元社,2012年8月の中でも指摘されているように,日本の政治家・外務省の国際交渉能力の程度加減を考えれば,交渉の中で御用聞き的にアメリカの言いなりになる,もしくは同調することはあっても,日本国民の意思・主張を通せないことは,寺島氏の分析能力/洞察能力から考えれば容易に理解している筈だ.,それら発言は寺島氏も背景を充分に承知の上で行っていて,何らかの意(アメリカ?財界?)を汲んだ上での発言かと思えてしまう.
とともに,寺島氏のそれら発言の中には国家戦略としての「日本国」は存在するのだが,日本国の主権者「主権在民」の,原発被害を受けた国民の生活や存在,民意が消えているのがとても気がかりだ.色々と理屈を述べてはいるのだが,もしかしたら寺島氏は民主主義の原点を忘れかけているのではなかろうか.危惧する.
国外のイラク戦争問題についてはしっかりと根を下ろした発言が出来ても(例えば,検証と展望「イラク戦争」岩波書店,2003年.「脅威のアメリカ希望のアメリカ」”開かれたナショナリズムとは”P149ほか,岩波書店,2003年),最も身近な国内問題ではさすがの寺島氏もアメリカ目線,世渡り目線となってしまうのか. 寺島氏の深い論理性や洞察力をこれまで高く評価し著者サイン本まで持っている者としても,上述の寺島氏の論理性を欠いた発言は誠に残念でならない(2012年12月31日).
② 当方からだけではなく,どこからかも指摘があったのか,その後(定かではないが2011年~2012年頃から)NHKは上述の呼び名を「財団法人
日本総合研究所」と「株式会社 日本総研」とに区別するようになった.
☆ 書籍紹介 「森が消えれば海も死ぬ」
松永 勝彦 著:「森が消えれば海も死ぬ 第2版」(講談社,2010年2月,800円)
元北海道大学教授の松永勝彦氏(現四日市大学)が,「森が消えれば海も死ぬ 第2版」(講談社ブルーバックス,2010年2月,800円)を15年余ぶりに改定出版した.化学的視点を軸に森と海の関係,生態環境のゆるやかで大きな循環メカニズムを解き明かし,その研究成果知識を社会に還元した素晴らしい書.環境に興味を持つ方や環境関連技術者には必読の普及版書籍.あわせて技術者とは人間の幸せとは何かも考えさせられます.( 2010年5月27日)
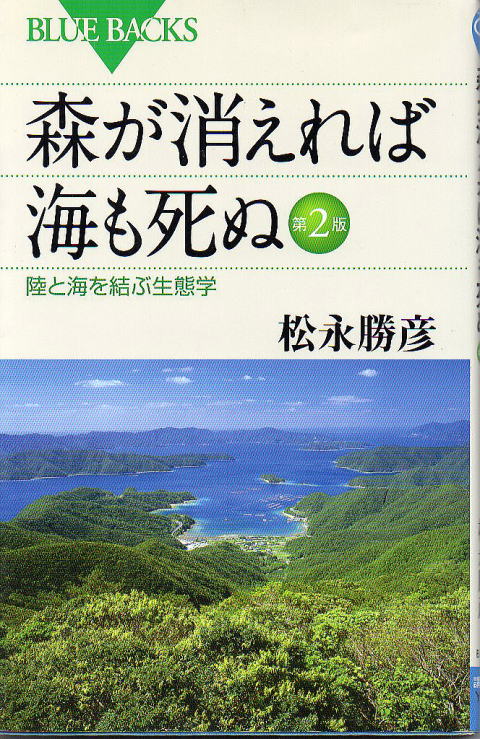
→ 実はこの本に書かれている環境メカニズム(河川上流にある森林の腐植土が生み出したコロイド状の鉄イオンが,降雨などによって流れ出し河川を通して海に供給される.この鉄を摂取してアマモ・昆布など沿岸の海藻類が生育繁茂し,それによって多様な生態系が維持され豊富な魚貝類を育む宝庫となる)は,私達が携わっている土壌/地質環境の汚染物質の分布や成因などの汚染構造を考える上でも参考になるものがあり,また共通性も有して興味深いものがあります.
------------------------------------------------------------------------
■ 興味あるホームページへのリンク(2011年1月)
広島大学の下記「地球資源論研究室」のホームページがなかなか実用的で興味深い.地球科学などの基礎知識を調べたい場合など辞書替わりに便利.またジャズ視聴ページなどへのリンクもあり,疲れた時の一時を過ごすにも最適.それにしても良く調べていますね.
http://home.hiroshima-u.ac.jp/er/index.html
------------------------------------------------------------------------
2005-2016 Hokusei Geotechnical Office All rights reserved.
書籍紹介などよもやま話のページ